- ホーム
- 日々のこと
- 同居人のこと
- 歩いてみれば好日
- 24年12月~25年4月
- 24年9月~12月
- 24年7月~9月
- 24年4月~7月
- 24年3月~4月
- 23年11月~24年3月
- 23年9月~11月
- 23年6月~9月
- 23年4月~6月
- 23年4月
- 23年2月~3月
- 22年10月〜23年2月
- 22年8月〜10月
- 22年5月〜8月
- 22年2月〜5月
- 21年10月〜22年1月
- 21年8月〜10月
- 21年5月〜8月
- 21年3月〜5月
- 21年1月〜3月
- 20年9月〜12月
- 20年5月〜9月
- 20年3月〜5月
- 19年10月〜20年2月
- 19年8月〜10月
- 19年6月〜7月
- 19年3月〜5月
- 18年12月〜19年3月
- 18年10月〜11月
- 18年8月〜9月
- 18年5月18日〜7月
- 18年4月〜18年5月17日
- 17年12月〜18年3月
- 17年11月
- 17年9月〜10月
- 17年7月〜8月
- 17年5月〜6月
- 17年3月〜4月
- 16年12月〜17年2月
- 16年11月
- 16年10月
- 16年9月
- 16年8月
- 16年6月・7月
- 16年5月
- 16年3月・4月
- 16年1月・2月
- 15年11月・12月
- 15年10月
- 15年9月
- 15年7月・8月
- 15年6月
- フォトギャラリー
- 染織のこと
- わたしの「う」
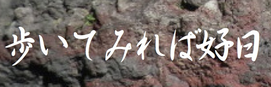
日本列島は、4つの大きなプレートがせめぎ合うちょうど上にあります。災害列島たる所以でもあります。
4つのうち、唯一フィリピン海プレート上にあるのが伊豆半島です。 およそ2000万年前の太平洋上の小さな火山島が、フィリピン海プレートに乗って北上し、本州に衝突して出来上がった伊豆半島。
なんだかまるで「ひょっこりひょうたん島」のようで、想像を搔き立ててくれます。 そして今なお、北へと本州を押し上げつつあります。
そんな伊豆に暮すようになってから、ずいぶんと月日が経ちました。 成り立ちの面白さ、独特の地層や伊豆半島固有の植物たち。
歩いて、歩いて、伊豆の自慢をしたいと思います。
●歩き始めた詳しいいきさつは→こちらをどうぞ

●●●お願い●●●
植物は類似した種が多く、
●メールでのご連絡先→ ori@ohnojunko.com
★★ 写真の左上に マークのある写真をクリックすると拡大写真が見られます。★★

NEW!
4月25日(金)箱根駒ヶ岳から神山へ
2015年に大涌谷で起きた小規模噴火から10年を経て、駒ヶ岳、神山への入山が解除されました。
初めて歩く山は新鮮で、ドキドキ、ワクワクです。

昨日の雨は上がったものの、今日もはっきりしない空模様です。
登山道はたっぷり雨を含んでズルズルでしたが、曇り空で気温も低めなせいか、外輪山と富士山の間に雲海が出来て、それはそれは美しい景色が見られました。


箱根駒ヶ岳が見えてきました。
神山、冠ケ岳、大涌谷などの中央火口丘の一つ、ところどころに溶岩流の痕跡が見えています。


ロープウエイでも登ってこられるので、ここもまた多くの外国人観光客の姿で溢れていました。
山頂はなだらかなカヤとの原になっていて、ぐるりと四方景色はすばらしい。



駒ヶ岳からいったん下り、神山へ。

群れ咲いた乙女たちです。タチツボスミレの仲間ですが、花は白、距が薄紫色。牧野富太郎博士が乙女峠で見つけたそうです。乙女峠はこのすぐ近く、一段と可愛く見えます。

四国ではなく四角からその名が来ているようです。
上弁が下っているためか、眉が下ってにっこりした顔に見えますね。花付きの良くないスミレなので目立ちませんが、葉が端正で特徴的なので見分けることができます。
4月21日(月)春の植物観察
標高およそ1200m、富士山の側火山の一つ、西臼塚の麓を散策しました。西臼塚の噴火口のヘリから火口を覗いたところです。


火口には白い綿帽子をまき散らしたようなミツマタの花と芽吹いたばかりのバイケイソウ。
小さな火口は「星の王子さま」がほうきで掃除していた様を思い出させるような・・・
わが家の庭にあっても、チャチャッと掃除できそうな大きさです。
永い年月を経て、穏やかにブナやミズナラ、カエデ、アブラチャンやマメザクラなどの豊かな森を育んでいます。


ようやく芽吹き始めた樹々の隙間から見える富士山は、近いだけあってさすがの迫力です。




さて、まずはネコノメソウの仲間たち。
鮮やかな黄色が美しいコガネネコノメソウ。萼裂片は真っすぐに立ち上がって、上から見ると四角に見えます。ネコノメソウの中では最も華やかなものの一つです。

あまりの小ささに見逃すところでした。
萼裂片が緑色なのでなお目立ちません。ツルネコノメソウ、タチネコノメソウにも似ますが、葉が対生でしたので、マルバネコノメソウかイワネコノメソウ。
悩むところですが、鋸歯の鋭さから言えばマルバネコノメソウではないかと。
平地ではジロボウエンゴサクがほとんどですが、この標高になるとヤマエンゴサクが見られます。ジロボウより花は大きくて、青味の強い色合いをしています。美しい造形ですね。
スミレは二種。
ヒナスミレでしょうか。珍しい。
今年も大方の早春の花たちが揃っていました。もう少し春が深くなってきたら、また訪れたいと思います。



4月16日(水)明神ケ岳
昨日は風が強く、今日も同じような等高線の並びでしたが、林間の登山道は穏やかで、春の陽射しが一杯でした。
下界ではすでに桜は終わっていますが、ヤマザクラ、マメザクラ、オオシマザクラが今を盛りの時です。


明神ケ岳に続く尾根は、ズドンとまっすぐに続いており、何カ所かに錆びて捨て置かれた鉄塔が立っていました。
帰って調べたところ、この尾根に、最乗寺から明神ケ岳に続くロープウエイを作ろうとしたようですが、断念し放置されたようでした。そんな時代もあったのですね。



明神ケ岳の尾根に出ると、やはり風は強いものの、景色は素晴らしい。箱根の外輪山がよく見えます。噴気を上げる大涌谷もすぐそこ。相模灘とはるかに三浦や房総までが一望です。


帰路の下山道で、アセビの木に倒れ掛かって宙づりになった倒木にシイタケ発見。
キノコバカ4人。代わる代わるに木に登ってはシイタケをゲット。この時期のシイタケは冬菇といって身がしまって美味しく、虫もついていません。
ニコニコで最乗寺奥之院まで下りてまいりました。

最乗寺は2大総本山、永平寺、總持寺に次ぐ曹洞宗の大寺院です。
広大な寺領に樹齢600年を越える杉の巨木の居並ぶ様子は、神聖で荘厳な空気が満ちています。その中に30を超える堂塔があります。
一度はゆっくり訪れてみたいと思います。



4月9日(水)岩戸山
こんなに近くなのに一度も来たことがないという友人夫妻と、十国峠から岩戸山、石仏の道を歩きました。
私はササっと歩きたい時や植物観察には午前中だけよく出かけて来ます。

出発地の姫の沢公園は、それはそれは見事な多様な桜の競演でした。寒い日が続いたせいか、いろいろな桜が一気に咲いてきたような感じです。十国峠辺りの高さになると、大島桜はまだこれからの感じ。例年なら4月の終わりに咲くマメザクラは、満開を迎えた木が多かったのは意外でした。


東光寺を訪ねたところ、ちょうど住職様がおいでで、本堂が開いていました。
私の好きな閻魔様と奪衣婆様。
奪衣婆様は立て膝で座っておられますが、女性のこの座り方は鎌倉時代を境にして変わることを伺いました。鎌倉時代や戦国時代は、女性も立て膝が一般的だったということを初めて知りました。
立て膝のこの奪衣婆様は、ずいぶんと古い時代に造られたものだったのですね。永い年月を経て、丸く風化した姿や顔の造作は、地獄の番人らしからぬ穏やかな風貌になっています。


岩戸山への道すがら、石仏の道も桜は満開。オオバヤシャブシの大木の横にも大島桜があったのですね。咲いて初めて気づきました。

本日のスミレ3種。
どこでも見かける一番馴染み深いタチツボスミレも、これだけ群れ咲くと見ごたえあり。
ナガハシスミレ、マルバスミレが咲き始めて、スミレの季節の中盤に差し掛かってきました。




今年は存分に桜を楽しみました。間もなく若葉の季節がやって来ます。

4月7日(月)函南原生林
今年の3月は寒い日が続き、雪もよく降りました。そのためか、林床の花たちは少し遅れ気味。

水辺の花たち。
スミレも遅く、ナガバノスミレサイシンがほとんど。やっと一つ、エイザンスミレを見つけました。












































